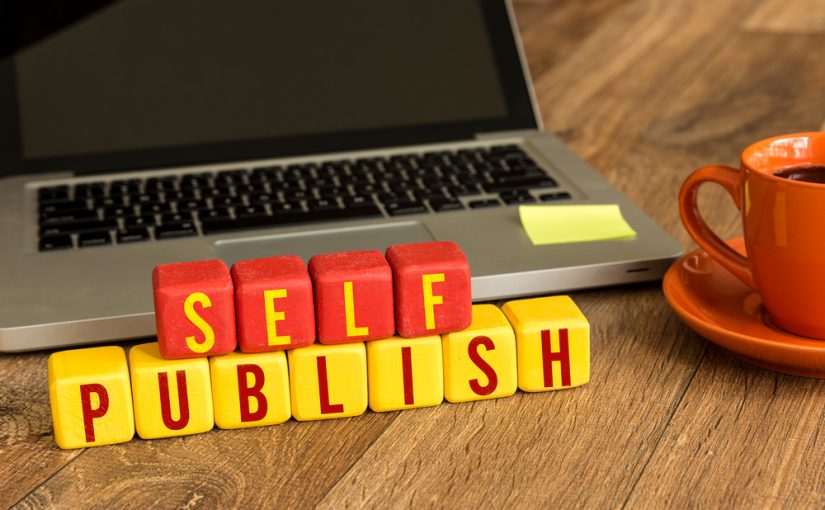「幼稚園で大事なことは?」
「幼稚園で子供に成長して欲しいと願っている」
「来年子供が幼稚園に入園する」
日本にはさまざまなタイプの学校があります。
幼稚園も日本の法律では、学校の一つに含まれています。
3歳から小学校に入学する前の子供が教育の対象です。
これらの学校では、幼稚園教育要領という基準に基づいて子供の教育がおこなわれていて、日本全国の子供が同じような教育を受けられるようになっています。
トピックス
幼児施設
幼児教育・保育の無償化について(日本語) : 子ども・子育て本部 – 内閣府
多くの幼稚園で重視されているのは遊ぶこと
日本各地にある多くの幼稚園で重視されているのは遊ぶことです。
遊びが重視されているのは、幼い時に多く遊ぶことにより、人間が成長するうえでさまざまなメリットがあるからです。
遊ぶことにより多くのことを学ぶこともでき、遊びを通してクリエイティビティを養うこともできます。
このような能力は小学校でより難しい勉強をするためには欠かせない能力であるため、教育の中に遊びを積極的に取り入れています。
こうした目的があることから、基本的に教科書などは使用しないで、子供に教育をしています。
幼稚園では子供のさまざまな能力を育むことを目標にしていて、重視しているのは子供に幅広い体験をしてもらうことです。
こうした体験を通して、子供がいろいろなことを感じたり、できるようになることが教育の目標です。
思考力や判断力を育てるために重要となること
思考力や判断力を育てるために重要となることは、子供が体験によって得た知識や技能を、生かすことができるようになることです。
自分の頭で考えて試行錯誤をしたり工夫をする能力も、子供が成長をするためには必要になります。
自分から勉強をしようという気持ちを育てることも重要になり、さまざまな勉強を自分からおこなうことで、人間性を成長させることができます。
園児が健康な体と精神を持つことができるようにすることも、教育の大きな目的です。
園の中で生活している子供が、自分のしたいことを見つけられるように手助けをしてあげる必要があります。
自分のやりたいことを見つけることができれば、子供は充実した毎日を過ごすことができます。
目標が見つかることで、将来の計画を立てながら行動をする能力も身につけることが可能です。
園児の自立心を育てることも重要
こうした能力は、自分自身で健康を管理して安全に暮らすためには必ず必要になります。
園児の自立心を育てることも重要で、自分でしなければいけないことを、子供が自分でわかるようになることが目標です。
園児の自立心を育てるために重要なことは、自分の生活している環境の中でさまざまなことに積極的に取り組むことです。
こうした取り組みの中で、子供は自分自身で考える力を育てることができます。
自立心が成長すれば、子供は諦めない心を育てることもできます。
諦めずに物事を最後まで行うことができれば、子供は物事を達成する喜びを味わえます。
このような達成感を味わうことも園児の成長にとっては重要なことであり、多くの達成感を味わうことで子供は自分自身に自信を持つことができます。
十分な自信がつけば、子供はどのような事にも積極的に取り組めるようにもなります。
幼稚園での生活は、子供の協調性を養うこともできます。
相手の思っていることや考えていることを理解できるようになる
園内には自分以外のさまざまな友達がいますが、これらの友達と関係を持つことより、相手の思っていることや考えていることを理解できるようになります。
こうした能力は他人との協調性を育てるうえで欠かせないものです。
他人と力を合わせることの大切さを学ぶことも、園児にとっては重要なことです。
同じ目標を達成するために、一緒に工夫したり考えたりすることによって、仲間と協力することの大切さに自分で気づくことができます。
仲間と協力して物事を成し遂げれば、一人でするよりも大きな充実感を味わえることも、子供は知ることができます。
初歩的な道徳心を身につけることも、園児にとっては重要なことです。
道徳心も周囲の人との関わりを通して学ぶことができます。
さまざまな経験を子供がすることにより、してはいけないことと良いことが自然に区別できるようになります。
子供が大人に成長するために非常に重要なこと
こうした能力が成長すれば、子供は自分の行動を客観的に見ることができるようにもなります。
道徳心が養われることにより、周囲の人の考え方に共感できるようにもなり、他人のことを考えながら行動できる人間になれます。
このような能力は、子供が大人に成長するために非常に重要なことです。
道徳心を身につけることで、社会のルールを守らなければいけない理由も、園児が自然に理解できるようになります。
自分の感情をコントロールできる能力も身につけることができ、周りの人と協調しながら行動できる能力も育ちます。
さらに成長すれば自分たちでルールを作ることもできるようになり、それを守ることの大切さもわかるようになります。
幼稚園では、家族を大事にする気持ちを子供に教えることも重要です。
家族に限らず、周囲にいるさまざまな人と関わる方法を知ることも、子供にとっては必要なことです。
まとめ
多くの人と接することにより、誰かのために何かができることを、子供は自分で知ることができます。
こうした経験を通して、子供は自分の得意なことを知ることもできます。