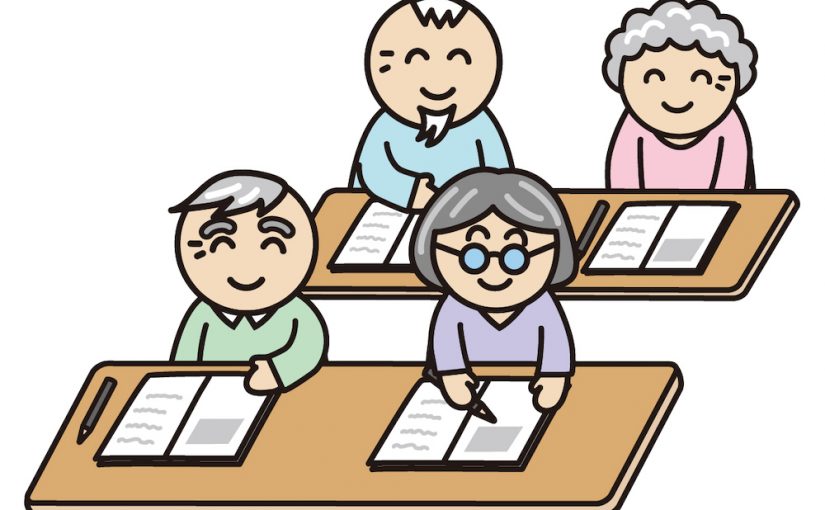2020年4月から施行される同一労働同一賃金制について、ご存知ですか。
これは正社員などに代表される正規雇用労働者と、パートタイマーや派遣労働者などの非正規雇用者の不合理な賃金格差をなくす制度です。
わかりやすく説明すると、「同じ仕事をしている社員は、同じ賃金で働こう」ということになります。
この制度にはメリットもありますが、導入にあたっての心配な点もあると指摘されているのです。
1)正規雇用者・非正規雇用者に関わらず近郊待遇が期待される
基本的には、同一労働同一賃金のもとであれば正規雇用者・非正規雇用者に関わらず近郊待遇が期待されます。
近郊待遇とは、業務内容や配置変更などが同じである限り、給与や福利厚生について同等に扱うというものです。
これまでの日本では、正規雇用者と非正規雇用者の給与格差や待遇差別などが問題視されてきました。
これを重く考え、今後は同一の仕事内容に携わる者であれば、賃金や待遇を同じにするべきではないかと考えられたのです。
これは非正規雇用者にとってはメリットといえます。
対象となる賃金は、基本給や時間外手当・賞与、役職手当などがあげられており福利厚生面でも改善が伺えます。
本来であればすでに労働法や雇用機会均等法という法律において、雇用形態において差別を行うことは禁止されているのです。
ですが、現状はそれを守らず雇用の格差は確実に存在しています。
2)同一労働同一賃金が施行されるメリット
同一労働同一賃金が施行されるメリットとしてあげられるのは、年々増加傾向にあるパートタイマーや契約社員などの非正規雇用者たちの賃金が上がる可能性があることです。
特に基本給などはこの規則に合わせて、賃金アップにつながるのではないかと期待されています。
また、同じ仕事・業務に携わっているという点で在宅ワークを行っている人や、テレワークを請け負っている人たちの基本給もアップする可能性があるのです。
このように賃金格差が発生しなければ、職業の選び方にも変化が現れる可能性があります。
働く側がより多くの選択肢から仕事を選ぶ、ということが出来るようになるかもしれないのです。
3)懸念材料について
一方で懸念材料も存在するのが、事実です。
雇う側、つまり企業においては今までコストカットの材料としていた、非正規雇用者の給与が上がってしまうと、負担が大きくなる可能性があります。
非正規雇用者の給与を上げた結果、総人件費が会社を圧迫するため、相対的に会社で働く全員の給与が下がってしまうという可能性もあるのです。
同一労働同一賃金の制度は、すでにヨーロッパなどで導入されています。
そのヨーロッパなどを観察すると、失業率が現在の日本よりも高いという問題が見えてきます。
そのため、導入されれば同じように日本においても、失業率が高くなるのではないかという懸念があるのです。
4)厚労省は「同一労働同一賃金特集ページ」を作成
日本の一部の企業では、すでに同一労働同一賃金を導入しているというケースもあります。
本来であれば、既存の法律によって雇用における差別はあってはならないことと定められているのです。
労働者を「コワーカー」と認定し、同じ業務である場合同じ賃金であるという制度を設定しているという企業もあります。
厚生労働省はこの制度の理解を促進するために、「同一労働同一賃金特集ページ」を作成し多くの国民に理解を求めている最中です。
実現に向けてのガイドラインや事業主への支援の在り方なども、特集ページでは説明されています。
労働者への支援としては、正社員とパートタイマーや契約社員の間に不合理な待遇差を発見した場合には、厚生労働省への窓口に相談をすることが可能となる見込みです。
これによって事業主への待遇の説明を求めたり、紛糾解決援助が利用可能となります。
窓口は全国の都道府県にある労働局雇用環境・均等部宛てになっており電話での相談が可能です。